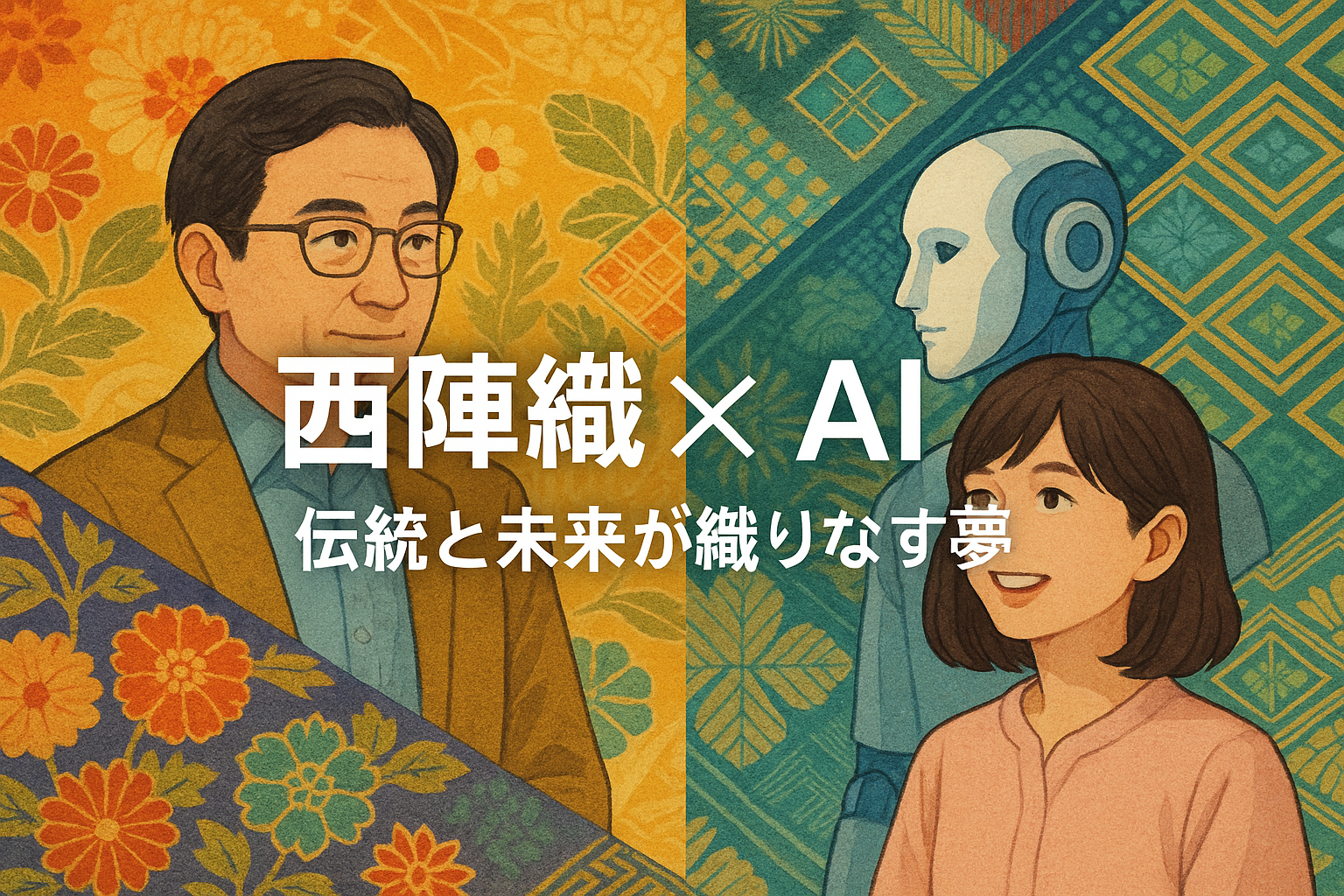
この連載は、AIとクリエイティブの現場をつなぐ対話シリーズ。ちょっと辛口で、でも思わずうなずくA先生と、好奇心が爆発中のX子が、毎回ひとつのニュースを深掘り。笑って「なるほど」となる、“ちょっと先の視点”をあなたに。
プロローグ
X子「先生、ちょっと見てください! 西陣織とAIが組んで、新しい柄を出してるってニュース。」
A先生「千年の手しごとに、最新の相棒か。うん、いい取り合わせ。抹茶にエスプレッソをひと垂らし、みたいな。」
X子「わ、それ絶対おいしいやつ。」
A先生「で、どこが気になった?」
X子「“AIが図案を提案→人が選んで織る”って流れ。置き換えじゃなくて、相棒感。」
A先生「そこ、今日の肝だね。」
1. なぜ西陣織にAIが必要なのか
工房の朝は、ふしぎと静かだ。戸を開けると、糸と糊のやさしい匂い。少し遅れて、奥からギィン、ガシャンと織機の律動。壁には色見本帳、差し込む光に糸の光沢がすっと起き上がる。
X子「でも、なんで“伝統のど真ん中”にAIなんです?」
A先生「伝統は“守る”だけだと痩せるんだ。“続ける”には、手を貸す存在がいる。いまの相棒がAI、というだけ。」
X子「AIが織るわけじゃないんですよね。」
A先生「もちろん。AIは図案の雨雲だよ。『こんなのは?』『これは?』って、アイデアの雨を降らせる。傘の差し方——どの滴をすくって布にするかは人が決める。」
X子「“発想の母数”を増やして、選ぶ時間を人に返す感じ、好きです。」
A先生「職人の目と手が届くように、前工程で視界を広げる。そういう使い方が、いちばん健やかだね。」
2. 工房の出来事:葉っぱが古典を越えた日
X子「AIが出した具体的な案、教えてください。」
A先生「壁一面にA4の紙がずらっとね。黒×オレンジの南国っぽい派手柄、そして——みんながちょっと息をのんだのが**“葉っぱで言い換えた古典文様”。」
X子「葉っぱで古典!? それってアリなんですか?」
A先生「アリかナシかは、人が決める。四代目の福岡さん、紙の端をトントン整える癖があってね。その手が、葉っぱの案で止まった。」
X子「“ビビッ”の瞬間。」
A先生「『これは、人間だとたぶんやらない置き換えだな』って。翡翠色寄りの糸を拾って、試しに織る。できた反物を窓辺で揺らすと、葉脈みたいなきらめきがすっと走る。」
X子「うわ、想像だけでもう好き。新しいのに、西陣の品がちゃんと残ってる。」
A先生「そう。外す勇気と芯の気品が、同じ布の上で手をつないでいる感じ。」
X子「でも、派手柄の方は?」
A先生「面白い。ただ“らしさ”との距離が遠かった。だから、今回は見送り。AIは秒で百案出せるけど、一番いい一案に“仕立てる”のは人だよ。」
X子「もしAIが“ピ◯チュウ柄の帯”出してきたら?」
A先生「ボツ。可愛いけどボツ(笑)。“らしさ”に合わないからね。」
3. AIは相棒、主役は人間
X子「職人さん、AIに抵抗はないんでしょうか。」
A先生「議論はある。でも結局、目線は同じなんだよ。“いいものを次へ渡す”。AIは敵じゃない。重い作業を軽くして、視野を広げる道具。」
X子「スピードを上げると、温度が下がる気がして怖いんです。」
A先生「むしろ逆。下ごしらえをAIに任せるほど、人は手触り、余韻、間(ま)に時間を使える。西陣の世界でいえば、糸の撚りが光にどう応えるか、季節の湿度で色がどう呼吸するか——そういう領分は、いまも人だけの仕事。」
X子「“わびさび”は、数式にしにくいですもんね。」
A先生「うん。あと、語って人を動かす熱。これはAIがいちばん苦手だ。いい布には、つくる人の体温がちゃんと残る。」
X子「今日の話、すごく前向きになれました。AIは速い足。人は道と景色を選ぶ頭。」
A先生「そして、行き先の“物語”を描く心。そこに西陣も、クリエイティブも、同じ血が通ってる。」
エピローグ
X子「先生、私も“自分の夢”を織ってみたくなりました。」
A先生「いいね。どんな技術が来ても、熱量と、まだない景色を描く力、そしてわびさびは君の手の中にある。糸車みたいにゆっくりでも、回し続ければちゃんと布になる。」
X子「じゃあ、次は“夢の描き方”の話、聞かせてください。」
A先生「約束しよう。次は、図案の“余白”をどう育てるか、だ。」
つづく。